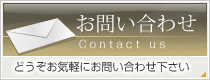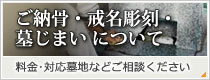お墓の豆知識都内 世田谷区 墓地・霊園・墓石のご相談は東菱石材へ!
「墓地」
お墓は、勝手にどこでも建てていいというものではありません。
たとえ自分の家の庭であっても、許可はされません。
それを規定しているのが、墓地・埋葬に関する法律です。この法律に基ずいて
公に墓を建てる為の場所と認められている一定の区域を墓地といいます。
「改葬」
お墓を移転する事。埋蔵・収蔵した遺骨を、他の墓地や納骨堂に移すこと。
改葬には、墓地を管理する市区町村役場、お寺など法的な手続きが必要になります。
「お墓を建てる時期」
お墓を建てる時期に決まりはありません。
お盆やお彼岸などひとつの筋目の前に建てる方もいらっしいますし、最近では
残された家族に負担をかけたくない、あるいは自分のお墓は自分で選びたい
ということで生前に建てる方が多くなっています。
「永代使用料」
墓地の取得は、お墓の土地そのものを取得するのではなく、お墓を永代的に使える
永代使用権を取得することですので、家の土地のように登記するわけではありません。
ですから、いらなくなっても売ることができません、墓石には所有権があります。
「開眼供養」
新しいお墓を建てた時に開眼供養を行ないます。
お墓に仏様を招来するための儀式です。この儀式によってお墓は拝礼の対象となります。
魂入れ、性根入れともいいます。僧侶にお願いして執り行います。
「寿陵」
生前に建てるお墓を寿陵といいます。
現代では墓地不足、残された家族に負担をかけたくないなどの理由で、
生前にお墓を確保しておこうとする人が増えています。
「お墓の地震対策」
最近のお墓はむかしのお墓と違い、色々地震対策がされています。
大きく分けて「耐震工法」と「免震工法」があります。耐震というのは、
金属やホゾ組みでガッチリ固定し、文字通り地震に耐えるもので
免震というのはガッチリ固定する耐震に対して、揺れを逃がす考え方で
作られるものです。
「お彼岸」
お盆と並んで大切な仏教の行事が春、秋のお彼岸です。
正しくは彼岸会とよばれ、昼と夜の長さが同じになる気候の良い季節に
行なわれ、ご先祖や自然に感謝をささげる日本独自の仏教行事です。
お寺の法事やお墓参りに行き、亡き人への思いをはせ、感謝のまことをささげます。
「納骨」
日本には遺骨を崇拝するという考え方があり、ほとんどが火葬で技術も高く
遺族は万感の思いを込めて集骨をします。肉体を捨てて白骨となることで
成仏できる、いつかは祖霊となって大地に還るまでの間丁重に供養を
するのがお墓であり、そのための納骨といえます。
「宗旨・宗派」
仏教はお釈迦様が元になっており基本的には一つのものです。
宗旨・宗派とはお釈迦様の弟子達が自分なりの解釈を加えて
伝えたものです。
「永代供養」
故郷を離れていて都会に住んでいるため、お墓参りができないなどの
理由から永代供養をお願いすることによって、お寺が永久に供養の
おつとめをしてくれる制度です。
「分骨」
遺骨を郷里の菩提寺に納めたい、生家のお墓にも納めたい、遠方でも手近でも
供養できるようにしたいなどの理由で遺骨の一部を分けて、二か所以上の
お墓に納骨することが分骨です。
「承継者が行方不明の場合」
墓地の使用権は永代使用権といわれる通り、永代にわたって使用権とその
承継を認められています。期限として法的には行方不明の場合七年死亡と
みなしますので期限以上行方がわからない場合は、使用権の名義変更が必要です。
「永代供養墓とは」
近頃生涯独身の人や子供のいない夫婦などが増えています。
お墓を継ぐ人がいない人のためのお墓で遺骨を預かり、供養や管理をすべて
お寺や霊園が永代にわたってやってくれるというものです。
「生前にお墓を建てると縁起がわるいの?」
寿陵が縁起が悪いなどというのは何の根拠もない迷信です。古代中国から
きたことばで、寿は長寿、長命、陵は皇帝のお墓を意味します。古くからおめでたい
意味として使われてきたので心配する必要はありません。